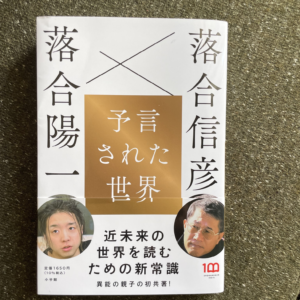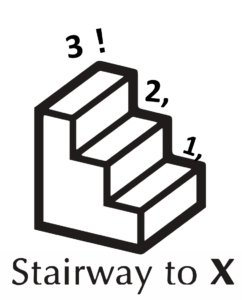「意味性」×Web3が世界をどう変えるのか気になってしょうがなくなる「ジャーニーシフト」
2019年に発刊されて「OMO」という言葉をバズワード化させた「アフターデジタル-オフラインのない時代に生き残る-」から数冊を経ての藤井保文さんの最新刊「ジャーニーシフト デジタル社会を生き抜く前提条件 」を読了しました。
「アフターデジタル」では、中国を中心に海外での新しい購買スタイルと、購買前後のやり取りの間で得られるデータを活かしたUX改善について述べられていた。
そして、「アフターデジタル」で紹介された事例は日本では見られない購買スタイルでありUXだったので、かなり強烈なインパクトとともに「OMO」という新たな概念を刷り込出だと思う。
2019年の「アフターデジタル」からも続編的な書籍は数刷発行されていたし、藤井さんもUXインテリジェンス協会やUX検定を立ち上げられるなど、「アフターデジタル」や「OMO」に続く継続的な発信はされていたみたいです(神谷はすべてを追っかけられていませんが)。
でも、今回発刊された「ジャーニーシフト」は、“海外ではなく、日本ではどうなる?”といった視点もかなり盛り込まれるなど、「アフターデジタル」からかなり大きくアップデートされたように感じました(「アフターデジタル」という言葉もタイトルから消えているし)。
「ジャーニーシフト」で新たに定義されているのは、「アフターデジタル」で述べられていた顧客に「利便性」を提供するUXに加えて、好き嫌いや所有したいを感じさせる「意味性」を提供することで接点を維持し続けたいと感じる関係性を構築すること。
そして、「利便性」もしくは「意味性」による「行動支援」。
この「利便性」と「意味性」による関係はすごく腹落ちした。
さらに、「意味性」とNFTをはじめたとしたWeb3で作られるであろう新たな関係性は興味深く新しい定義だと感じた。
ただ、「意味性」とWeb3の部分が神谷にはまだまだ消化不良で、「意味性」とWeb3の部分だけでももっともっと深堀りしてほしいし、深掘りしてみたくなりました。(ここだけでもかなり分厚い本になりそうですが。。。)
「利便性」を提供しての関係値は多くのプレイヤーを巻き込んだ長いジャーニーで多くの価値を提供できる(プラットフォーム的な)仕組みづくりが必要なんだろうけど、ここはGAFAMなどのグローバル勢や国内ではYahoo!&LINE&paypayなどのZホールディングスや楽天経済圏などがガチンコで勝負する大きなフィールドになると思う。
一方で、「意味性」はアーティストやゲーム、IPなどのマスコンテンツからインディーなコンテンツまで、大きいフィールドも小さいフィールドも混在して成立するし、大きければいいというわけでもない。
そして、小さなフィールドが化ける可能性もすごくある。
そんな「意味性」をWeb3により価値化された新たなジャーニーや「行動支援」がこの世界をどのように変えていくのか?がすごく気になる一冊でした。
*誤読・誤解、表現間違えなどなど、あると思います。その際はご容赦ください
(ご指摘いただけると大変ありがたいです)